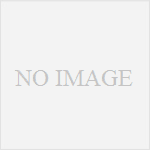酸素欠乏症、硫化水素中毒を防ごう
本年8月、埼玉県行田市で下水管の点検をしていた作業員1人がマンホール内に転落し、助けようとした作業員3人も転落して亡くなる事故が発生しました。その後の報道によると、硫化水素中毒、酸素欠乏症の可能性が高いとのことです。7月に同じ場所で作業を行った際、硫化水素濃度に問題がなかったとのことで、転落防止の安全帯(ハーネス)や空気呼吸器は使用されていませんでした。事故後、硫化水素濃度は150ppm以上(労働安全衛生法における管理濃度は10ppm)を計測したとのことです。詳細な測定の時間や位置などは不明ですが、事故発生当時、現場では硫化水素濃度700ppm以上、あるいは酸素濃度6%未満のいわゆる無酸素空気といった、短時間に意識を失うような状況がなかったのか、大変気になるところです。
わが国では酸素欠乏症・硫化水素中毒は毎年起きており、厚生労働省の資料によると、過去10年間の平均被災者数はそれぞれ6.8および5.6人/年でした。特徴として、致死率が高いことや、二次災害が起きやすいことが指摘されています。マンホール、タンク、汚水槽・汚泥槽などは事故が発生しやすい場所として要注意です。原因としては、作業環境中の酸素濃度・硫化水素濃度の測定未実施、換気未実施、空気呼吸器の未使用などが、また管理面での問題点としては、酸素欠乏危険作業主任者未選任、安全衛生教育不十分、作業標準不徹底などが多くなっています。特に、酸素濃度・硫化水素濃度の測定は重要で、時間とともに変化する可能性があるため、一回のみの測定では不十分です。
全国で整備された下水道は、完成後長い年月が経過し、老朽化のため点検や更新工事が必要になっています。作業時に基本的な事故防止対策がきちんと取られ、尊い人命が失われることがないことを願うばかりです。
(K.A./有澤 孝吉(富山産業保健総合支援センター産業保健相談員)2025年11月)