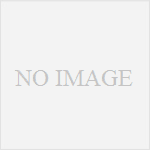チームを育てる心理的安全性
近年、職場における「心理的安全性」が注目されています。最近では、学校でも学級づくりや人間関係の構築に、この考え方が活用されはじめています。
心理的安全性とは、チームのメンバーが対人関係におけるリスクを恐れずに行動できるという共有された信念を指します。たとえば、会議の場で、自分の意見を安心して述べられたり、助けを求めたり、失敗を正直に報告しても責められないと感じられるような雰囲気のことです。このような環境は、生産性や創造性の向上、職務満足感の増加など、組織や個人にさまざまな影響をおよぼすことが分かっています。
心理的安全性が広く注目される契機となったのが、Google社が実施した「プロジェクト・アリストテレス」です。これは、「全体は部分の総和に勝る」というアリストテレスの言葉にちなんで名付けられたプロジェクトで、プロジェクト名が示唆するとおり、効果的なチームづくりの鍵は、誰がチームのメンバーかよりもチームがどのように協力しているかにあるとの結論を導きだしました。その最も重要な要素として挙げられたのが、心理的安全性です。
ただし、心理的安全性は高ければよいというものではありません。無責任な言動まで容認されるようになると、かえってチームの健全性が損なわれる懸念もあります。心理的安全性を高めると同時に、一人ひとりが自らの言動に責任を持ち、相手への敬意を忘れないことが大切です。心理的安全性においても、「親しき仲にも礼儀あり」や「過ぎたるは及ばざるがごとし」といった意識が求められるのかもしれません。
(カイト/大平 泰子(富山産業保健総合支援センター産業保健相談員)2025年8月)