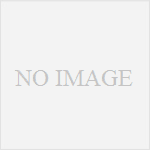精神科における診断について
精神科診断の曖昧さについて、質問を受けることがある。その原因は診断の方法にあると考えられる。学生の頃、sickness,illness,diseaseとあるが、精神疾患の大半は、漠然とした体調不良のsicknessではなく、明確な身体的原因があるdiseaseでもなく、まとまった症状が長期に続くillnessであると教えられた。この考えは、現在でも通用するものと考えられる。精神科診断は、その時点の精神病理学的症状によって行われるため、そのまとまった症状が時間の経過によって変化すれば、診断も変化していくわけである。代表的なのは、うつ病として治療されてきた患者さんが躁状態を発現した時点で双極症(躁うつ病)に診断が変更され、治療法も変わってくることになる。
このようなことは日常茶飯事である。また、1960年代まで、精神科診断が、文化的背景によって一致しないことも問題であった。精神分析が主流だった米国と英国とで、統合失調症の診断一致率を調査したところ、米国では統合失調症の診断の範囲が広いことが判明し、一致率が極めて低かった。この結果を受けて、国際的に通用する診断基準の作成が必須であると判断され、1970年代にアメリカ国立精神衛生研究所(NIMH)のSpitzerらを中心に、当時米国では少数派であったネオクレペリン学派(セントルイス学派)の理論を採用して、研究診断基準(RDC)が形作られ発表された。RDCは研究分野では世界的診断基準となっている。しかし、RDCはあくまで、研究が主体であったため、臨床にはなじまない面もあった。そこで、精神疾患の原因は一時棚上げして、一定の精神症状がみられる群に診断名をつける操作的診断法を導入し、症例を集積して、原因に迫ろうという意図のもとに「精神疾患の診断と統計マニュアル第3版、DSM-III」が1980年に刊行され、国際的に広く使われるようになった。DSMは改定を重ねて、現在はDSM-5-TRとなっている。次回は、DSM後の展開について述べたい。
(眠り猫/木戸 日出喜(富山産業保健総合支援センター産業保健相談員)2025年6月)