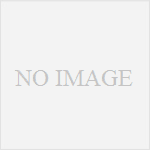震災復興と産業保健
震災復興には地元の人のみならず全国から復興支援のために尽力いただいている。その形はボランティアだけではなく、仕事として長期的に支援をいただくケースもある。
昨年発生した能登半島地震において復興支援に尽力する企業への産業保健活動を行う中で、ご家族の写真を飾りながら単身赴任で業務に励む姿を拝見し、「安全に、健康に、ご家族のもとに帰っていただくまで」と強く心に刻んだ。震災から1年半以上が経過し、昨年9月、今年8月にも豪雨に見舞われている。特に先月はお盆休暇と重なる時期で、この機会にご家族のもとに一時帰省する予定が土砂災害への警戒のために叶わなかったケースもあっただろう。まだ先が続く復興支援、心身ともに健康でいられるよう支援していくことも必要な産業保健活動といえるのではないか。
産業保健が担当する範囲は広い。広くてその一部にしか着目することが出来ていない産業保健スタッフもいるだろう。震災復興とはその特殊性に注目されがちであるが、「安全に、健康に、帰宅する」「『いってきます』と出勤した人が、同じ状態で『ただいま』と帰宅する」という根幹は普段の産業保健活動と違いが無い。ご家族のもとから仕事のためにお預かりしている間に、日々の短期的だけではなく長期的にも健康を害さない、悪化させないように、健康管理のみならず有害物質・要因を始めとした作業管理・作業環境管理で悪影響を受けないように、個人だけではなく集団、会社、社会を通して支援していくことが産業保健活動だ。産業保健活動を見つめ直す機会は各々にきっかけがあるだろう。これを私のきっかけの一つとして紹介するとともに、これを読んだ方々にも「想うこと」ができると願いたい。
(ひばり/溝口 里美(富山産業保健総合支援センター産業保健相談員)2025年9月)